
どもども、ゆる猫です。
20代から40代の若い世代の方の中には、

- 将来年金が十分にもらえるのか不安
- 働いて生活にゆとりのある今のうちに、老後の暮らしに備えておきたい
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そのような方にオススメの老後に備えるための制度iDeCoについて、お話したいと思います。
iDeCoとは?
個人型確定拠出年金iDeCoとは、基本的には20歳以上60歳未満の方向けに老後の資産形成を後押しするために国が用意した私的年金制度になります。さらに国が後押ししている制度のため、掛金が全額所得控除の対象になるなど税制面で非常に優遇されています。
掛金の上限については、人によって異なってきますが、最低5,000円から1,000円単位で加入者自身が掛金を指定できます。※指定した掛金の拠出額は、1月から12月の間に年に一回変更することが可能
掛金の拠出額の上限はいくら?
自営業者やフリーランスなどの国民年金第一号被保険者の場合
最大で 月額 68,000円
※ただし、国民年金基金の掛金や付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した金額が上限
厚生年金保険の被保険者など国民年金第二号被保険者の場合
勤め先が
①厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合
月額 12,000円
②企業型年金のみを実施している場合
月額 20,000円
③企業型年金や厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合
月額 23,000円
会社員の方の場合、勤め先が上記のどれに当てはまるか分からないときは、会社の人事など労務担当の窓口に確認してみましょう。
専業主婦(夫)等の国民年金第3号被保険者の場合
月額 23,000円
iDeCoのメリットは?
掛金の所得控除
iDeCoの制度で最も大きなメリットは、何と言ってもiDeCoの掛金の拠出額が全額、所得控除の対象となることだと思います。
日本では、iDeCoの他にもNISAなどの資産運用時の税制優遇制度はありますが、掛金そのものが税金の控除対象となるようなものは、iDeCoを除いて他にないため、この点が一番大きなメリットと言えるでしょう。
その際の節税効果については、加入者の年収や掛金の拠出額にもよりますが、極端な話、iDeCoに加入して、掛金を全額元本保証型の商品で運用しても所得控除の節税メリットだけで、人によっては銀行預金で預けておくよりもお得になる場合もあります。※ただし、元本保証型の商品のみで運用した場合、月々の手数料分、元本は目減りしていきます。
運用益の非課税
通常、投資などの資産運用から得られる利益については、およそ20%程度の税金が課されますが、iDeCoの拠出額を運用した際に得られた利益については、現在課税が停止されており非課税となるため、効率的に資産形成を行うことができます。
受取時の税控除
受け取る際には、一時金としてまとまった金額で受けとる場合には退職所得控除が適用され、年金として受給する場合には公的年金等控除の対象となります。
ただし、こちらの控除については、加入者の状況(受取時の所得額、勤め先からの退職所得の有無、退職時期、年金受給額など)によって控除の対象となる上限が異なるため、各自注意が必要になるかと思います。
iDeCoのデメリットとは?
運用資金を自由に引き出しできない
iDeCoは、老後の資産形成を後押しするための老齢資金という性質上、原則60歳までの引き出しができません。さらに、加入年数が10年に満たない場合は、加入年数に応じて、さらに引き出しできる年齢が上がっていきます。
先ほど紹介した掛金の所得控除や、運用資産の非課税といったメリットを最大限活用するためには、上限いっぱいの掛金をできるだけ長い期間運用することとなりますが、加入年数が長くなるほど運用資産の拘束される年数が長くなるデメリットも大きくなります。
若い世代の加入者の場合、結婚、車の購入、育児・教育費用などのまとまった資金が必要な場合でもiDeCoの運用資産からは引き出せないので、ご自身のライフプランに合わせて計画的な掛金設定での運用をオススメします。
元本割れのリスクがある
毎月拠出された掛金を運用するため、運用資産にはもちろん元本割れのリスクがあります。
iDeCoの取扱商品の中には元本保証型の商品も用意されていますが、全額元本保証型の商品で運用した場合、運用にかかる手数料分元本が目減りするということだけは頭に入れておきましょう。
加入時・運用時・受取時に各種手数料がかかる
iDeCoでは、加入時・運用時・受取時に国民年金基金連合会、信託銀行、運営管理機関に対して各種手数料がかかる場合があります。
支払い先は三者ありますが、基本的に加入者の拠出額から差引され、加入者がそれぞれ個別に支払いする手間はないのでその点はご安心ください。
iDeCoの手数料はいくら必要?
国民年金基金に支払われる手数料については、
加入時に 2,829円(税込)
運用時に
口座管理手数料 月額 105円(税込)※掛金を拠出しない運用指図者は不要
還付手数料 都度 1,048円(税込)※還付金が発生した場合のみ
信託銀行に支払われる手数料については、
運用時に
口座管理手数料 月額 66円(税込)
還付手数料 都度 440円(税込)※還付金が発生した場合のみ
受取時に
給付手数料 都度 440円(税込)
その他、営管理機関に支払う手数料については、各運営管理機関によって異なるため、それぞれの公式HPなどをご確認ください。
運営管理機関を選ぶポイントは?
取扱商品のラインナップ
iDeCoは税制の面で様々な優遇制度はありますが、そもそもの掛金を運用する商品が「信託報酬の高い商品」、「運用成績の悪い商品」ばかりですと、運用資産を効率的に増やすことができません。
運用資産の額が増えてくると商品の信託報酬の1%の差でも、運用額100万円では1万円の差になり、運用額300万円では3万円の差になってきます。口座管理手数料の数十円や数百円の節約をして、こちらの信託報酬の差で気づかぬうちに大きく損をしてしまうなんてことにならないよう気をつけましょう。
各種手数料
各種手数料については、運営管理機関によって異なる場合があります。先に述べた信託報酬の違いの方が判断基準として優先度は高いと思いますが、取扱商品のラインナップで候補を絞った後は、各社の手数料を基に判断しても良いかと思います。
今からiDeCoに加入するなら、オススメは楽天証券かSBI証券
私自身が、もし今からiDeCoを始めるとしたら、取扱商品の内容や各種手数料から判断して楽天証券かSBI証券で始めます。
※実際には、現在、大和証券のiDeCoに加入していて、各種手数料については満足していますが、取扱商品のラインナップに物足りなさを感じているため、運営管理変更手数料は、4,400円かかりますが、変更の手続きをしている最中です。 ※2021年6月に大和証券からSBI証券のiDeCoに乗り換えしました。
まとめ
- iDeCoは、国が用意した老後に備える私的年金で、国民年金や厚生年金に加えて老後のために備えたい方向けの制度
- 税制面で非常にお得だけど、老齢資金という性質上、原則60歳まで引き出しできないため、ご自身のライフプランを踏まえた計画的な掛金設定が大事
- どの運営管理機関を選ぶかは、取扱商品のファンドの信託報酬や運用成績など、商品のラインナップが非常に重要
以上、今回は老後に備えたい方向けに個人型確定拠出年金iDeCoについてお話いたしました。
今回、紹介した内容が皆様のしあわせに暮らしていくためのヒントになれたら幸いです。

ではではー(^・ω・)ノ”

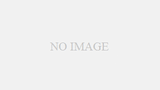
コメント